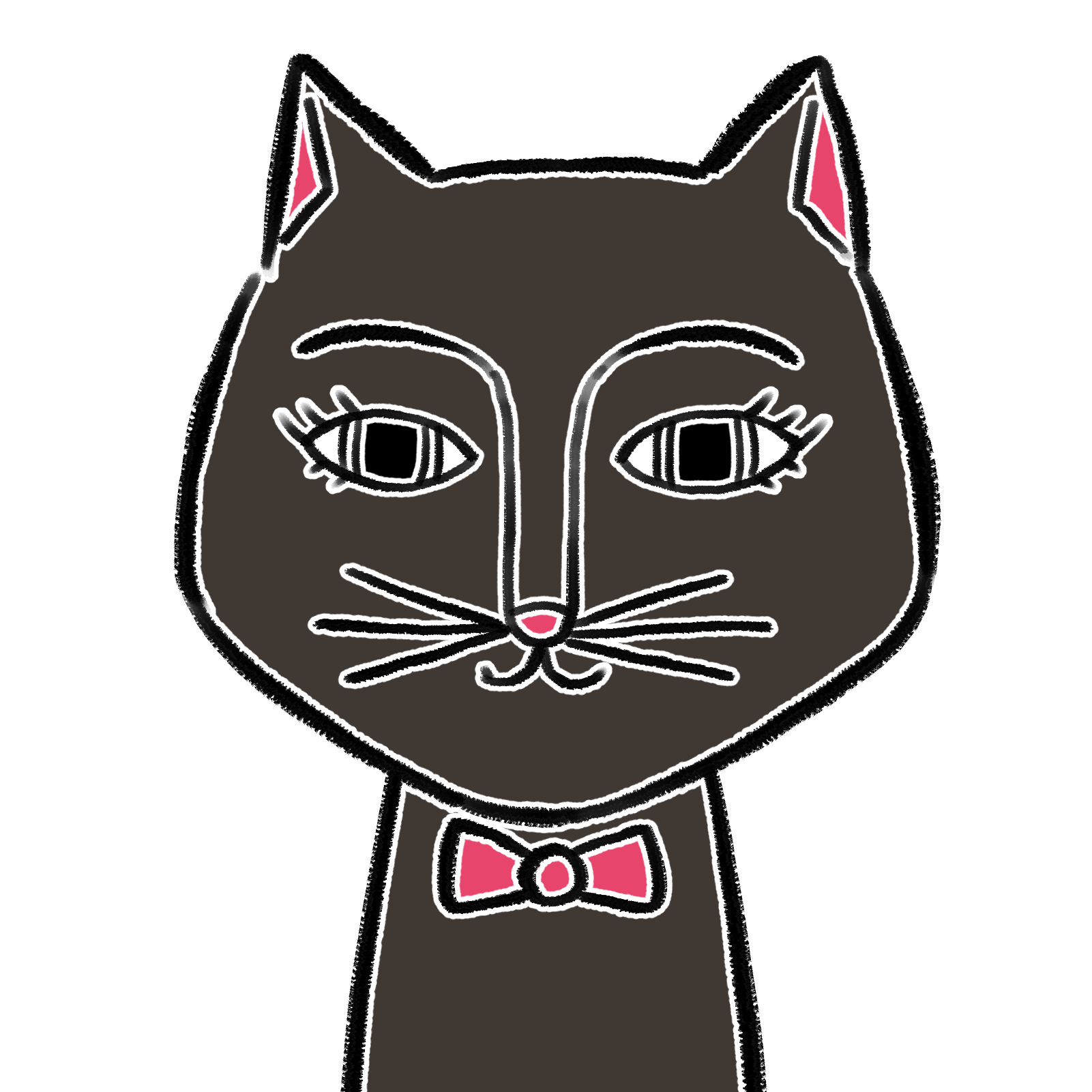
ネーロ
ビアンコ先生大変です〜!
楽譜にシンコペーションというリズムが出てきました〜!僕、どうやって演奏したらいいんでしょ〜??
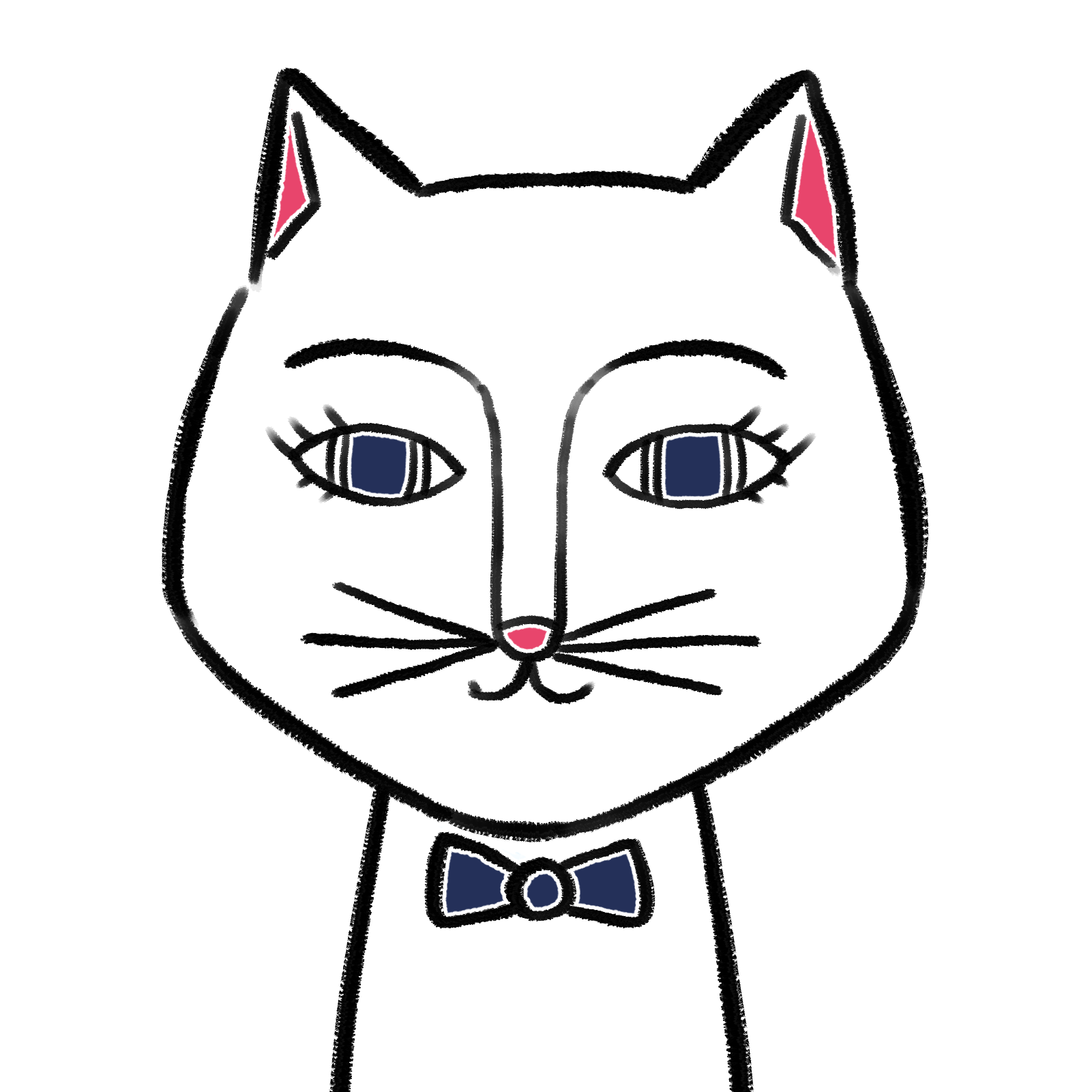
ビアンコ先生
ネーロ、それじゃあ今日は一緒に
シンコペーションの楽譜の読み方を見てみよう!
シンコペーションの楽譜例

上の楽譜は4分の4拍子、一小節間がシンコペーションのリズムで書かれたものになります
実はこの楽譜は、下のように書き直すことができます

シンコペーションのリズムは下の楽譜のように、楽譜の裏拍と表拍が繋がることによって独特の躍動感が生まれます、ピアノやドラム、ギターなど様々な楽譜に登場する個性豊かなリズムです

プロの指揮者が初心者の方へおすすめする楽典の本3選こちらもおすすめですよ!
シンコペーションの有名な曲
シンコペーションが多用されている音楽に、ボサノヴァがあります
「イパネマの娘」などが有名ですね
ジャズはもちろん、クラシックの曲などの古い音楽のスタイルにも、シンコペーションのリズムはたくさん出てきます
よくCMなどで使われているモーツァルトの「交響曲第25番」もシンコペーションのリズムの持つ躍動感を活かした曲です
↓色々な曲を試しながら演奏してみたい!という方におすすめですよ!
シンコペーション練習の仕方

先ほど出てきたシンコペーションの楽譜をもう一度みてみましょう
シンコペーションは演奏しているうちに、急いでしまうことのあるリズムの一つです
ですので下の楽譜のように表拍と裏拍を繋いでいるタイをとってしまい下の楽譜のように八分音符単位で一度練習してみて、その後再びシンコペーションのリズムに戻すと上手に演奏できるようになりますよ!
↓自分の演奏がテンポ通りできているか確認できるメトロノーム(チューナー付き)は便利ですよ!
ヤマハ(YAMAHA)
¥4,695 (2024/09/27 22:04時点 | Amazon調べ)
両手を使ってリズム感を鍛えたい方はこちらのリズムゲーム(中級)にチャレンジしてみてくださいね!




コメント